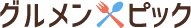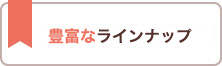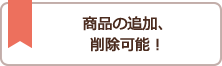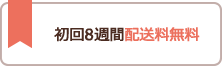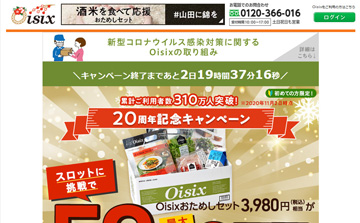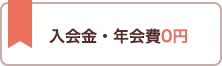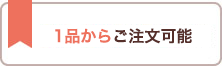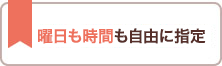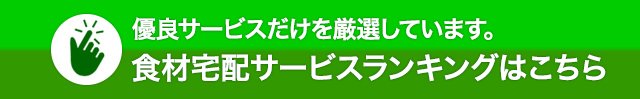目次
レンタル農園の特徴とは?
レクリエーションや生きがい、自然に親しむなどの目的で、地域住民などが小面積の農地利用を行うことを、レンタル農園と呼びます。
貸し農園や市民農園といった呼称でレンタル農園の魅力が多く紹介される近頃では、食育や企業の福利厚生などで利用される事例も増え始めています。
また海外では、レンタル農園に対してクラインガルテン、体験農園、レジャー農園といった呼び名を使うこともあるようです。
日本におけるレンタル農園の歴史と沿革
日本で初めてレンタル農園が開設されたのは、大正13年のことだと言われています。
第二次世界大戦により一時は全消滅した市民農園も、農林水産省によるレクリエーション農業という認定により、少しずつ開設の動きが加速するようになりました。
また市民農園整備促進法が制定された1990年以降は、附帯設備の整備も可能になったことにより、レンタル農園や市民農園の使い勝手が更に良くなっているようです。
レンタル農園にはさまざまな開設方法がある
全国各地で人気の高いレンタル農園には、下記のようにさまざまな開設方式が存在しています。
・市民農園整備促進法
・農園利用方式
・特定農地貸付法
・農業体験農園
・宅地・公園・ビル屋上といった農地以外での開設
法律的な視点より厳密に考えれば、体験農園というカテゴリは農産物の区画販売に位置づけられるとされています。
しかし利用者からすると市民農園と類似のサービスとなるため、厳密なシステムが異なっても、レンタル農園としてカウントされることもあるようです。
レンタル農園の価格・利用料の相場とは?
農家や自治体、農業協同組合の開設するレンタル農園は、1万円ほどの年会費で15~30平方メートルほどの区画利用ができるケースが多いようです。
これに対して農業体験農園で設置するレンタル農園に近いものについては、30平方メートルほどで3~5万円の年会費が相場となっています。
農業体験の場合は、種苗の用意や農機具の貸出、月数回の講習会なども行われているため費用としては若干高くても利用者にとってはコストパフォーマンスの良い内容となっているようです。
無農薬野菜や有機野菜をレンタル農園で作る
レンタル農園を上手に利用すれば、食材宅配・通販サービスで購入できるような有機野菜や無農薬野菜の栽培も可能です。
しかしこうした農園を利用した栽培や収穫に多くの手間がかかる実態を考えると、オーガニック野菜などを手軽に食べたい人には食材宅配サービスの利用の方がおすすめ度は高いと言えるでしょう。